Tomas Norton ‘Ordinal’ 第2章
かつてノルマンディに、様々な身分を股にかけ人々を騙した修道士がいた。この術について完全な知識を握っている、彼はそうした空疎な自負心で腹中を満たしてからというもの、それまでのように、粗暴な慰みに溺れることで己の理性を失わせることがなくなった。私は、実例を挙げるための短い物語として以下にこれを記し、そうすることで、この者の荒唐無稽な熱情を許そうと思うのである。
この僧侶は、フランスで放浪の人生を送るさなか、神への祈誓を忘れて欲望に溺れた。その果てにこの王国へやってきて、あらゆる人に自分が錬金術をすっかり会得していると信じさせようとしていた。彼はそれを、さる秘法の書から学び取ったと吹聴していた。僧侶は権力の獲得に熱心であり、後世に渡って己の名が輝かしく伝わり、この島に彼の名声が永遠にうちたてられることを望んでいた。彼はいつも、もうすぐ自分の手に入ると思いこんでいるその莫大な富の使い道に頭を悩ませており、ついに「みよ。この問題の解決を手伝い、この望みの充足を補助すべき、信頼に足る人物の居場所がわかったぞ。ソールズベリー平野に輝かしく、あっという間に、しかも一マイル毎に、壮麗なる十五の大修道院を建立するのだ」と独りごちた。この構想を実現しようと、僧侶は私のもとにやってきたのである。彼は計画の全体像を私の前に広げ、同時に助言を求めた。私は、聖ジェームスの聖堂でその名を明かさぬ誓いを立てたが、身贔屓はするまい、私はこの彼の愚かな企てを以下に語ろう。僧侶は、この輝かしい術に熟達していることを力説すると、王のために働くことの他には何も望んでいないこと、そして件の大修道院建立のために土地を購入する枢密院の許可が欲しいということを語った。その費用を工面するのは、彼には簡単なことであるそうであったが、その一方で、土地を手に入れるにあたり場所や相手、方法について、いたく悩んでいたというわけである。その高邁な事業を説かれると、私は彼の学んだ知識が神学的な学問としてどれ程のものかを試そうと思った。そして、彼がこれらの学識の分野を探求するには、憂うべき有様であることがわかった。けれども彼の事業からは、さらに学び取れるところが期待されるかもしれず、私は自制し、己の誓いを守りつつこう伝えた。この計画には、王の御前に出せるほどの充分な重要性がなく、その主張が実現可能である証明がなければ、皆が皆、無駄な話とみなすことであろう、と。しかし修道士は、すでに火中に物質を設えており、これが彼に必要なところをすべて供給してくれるはずであった。そして四〇日の間には、その力説するところがまことであると、高らかに立証できるのだと答えた。私は、それで最早これ以上を問い詰める気もなく、ただ彼の言った時間を待とうと答えた。しかし、彼の定めたその日がやってくると、修道士の方術は霧散し、大修道院建立という壮大なる計画も霧消した。詐欺師でもあったかのように彼は、苦い屈辱と狼狽とともに行方をくらませた。それから間もなく、彼は多くの情に厚い多くの人々を騙しては、再びフランスへ戻っていったことを知った。十五の大修道院、信仰の座、至聖所そして学舎という大望の理念が、軽率なる僧侶とともに軽々しく消え去ってしまうのは、いたく残念なことに思われる。また、そうした人間が、十五もの大修道院を建立できると自ら思いこんでいたことは、また驚くべきことでもある。この聖なる術の知識を学び取るために、恭順の誓いに生きることが出来ず、背教の浮浪者として流離わねばならないとしても。しかし私は、術がまさに聖なるものであるがゆえ、虚偽の詐欺的な人物には決して到達しえないということをすでに繰り返し述べたのであった。更に別の例を挙げて、我が意図するところを明らかにしよう。あたかもレイモンド・ルルや修道士ベーコンのごとく、己がこの術に深く熟達していると思い込んだ男がおり、自らを比類なき者と称するほど高慢であった彼は、ロンドンからほど遠くない小さな街の司祭であり、説法がなかなかに巧みであると巷には評判であった。この男は、我々の術の秘密を発見したと心底思っていて、その名声を高めようと、生活者や旅人たちの便宜を図り、テムズ河に橋を架けようと計画したのであった。この偉大で巨大な建造物を眼にする者はひとりとして賛嘆せぬはずはないのに、しかしこの計画に一肌脱ぐ者は誰もいなかった。それは、燃えるような黄金に装飾され、かつてない尖塔を備えたものとなる筈であった。男は、これより現実となろうとしている前途をあつく語った。その橋は永久に壊れることなく、闇夜にも遠方から眺めうるもので、決して衰えぬ偉容を誇るのであった。男は、さらにこの大事業を運営する最善の方法に思いを馳せた。まず彼は、充分な数の燃える松明を設置するということを思いついたが、この慈善事業を管理する者が男の死後にこれを軽んじ、それに割り当てられた費用を別のことに費してしまうのではないかと恐れた。そして男は、夜ですら橋が遠方にも全景を示し、あらゆる方角に光彩を放つよう、荘厳な輝きをもつ宝石や紅玉をつかおうと結論したのである。しかし、かくして男は新たな懸念に至った。そのような紅玉が一体どこで手に入るのか、そして世界のあらゆる国々を旅してでも、これら宝石の充分な量を獲得する賢く頼りになる人物がいないものか。こうした妄想で、男はかなりの不安に陥り、その姿を影のように痩せ衰えさせたほどである。もちろんこうした間にも、男は自分が我らの術の秘密を体得したものと固く信じていた。しかしその年の終わりには男の術と、その物質は希望とともに消え去った。彼がガラスの容器を開けてみると、そこにあるものは金でも銀でもなかったのである。かくして男は激情に駆られ、心痛のあまり自身を呪った。彼は財産の全てを使い果たし、残りの人生を貧困の内に過ごした。彼についてこれ以上記すことがあろうか、この事例はその問題点を雄弁に物語っている。
博学の者、そして学舎に通う学徒らは、こうした愚かな人物の悲劇の結末を耳にして、注意を喚起すべきである。かようなことに常なる配慮を欠けば、自身にもまた同様のことが降りかかると肝に銘じるのである。学徒の多くは、それが誤りであっても、書物に大胆な断言を見つけてしまうとあまりに軽々しく結論を受け容れがちである。こうした懐疑なき容易なる軽信は、貧困と心痛を引き起こす原因となる。そうした煽りに唆された期待は虚しい歓喜であり、紛れもない愚者の楽園である。だが我らの術の真の息子らは、その希望をただ神にのみ留める。神とともにあらねば、あらゆるものは妄想であり失敗の因となることを知っているからである。そして、あらゆる知識の起源を知らぬ者は、その探索を成功へと導くことが出来ないことを知っている。嗚呼、神なしには何者も悟りには至れず、術の開陳が人の耳に語られようとも、信仰なくばそれは虚しく通り過ぎるだけであろう! 嗚呼、神よ。あらゆる神聖なる成就への尽力は、神の御心によりて来る! 始めから終わりまで、神こそがあらゆる善事の源である。さて私は、愚かな探求者の空疎な望みが、喜びともなるべきところを引き起こしうることを汝に語った。聞くがよい、この術が禍根となって多くの者の期待をゆゆしき失望へと変えた不幸についても記そう。
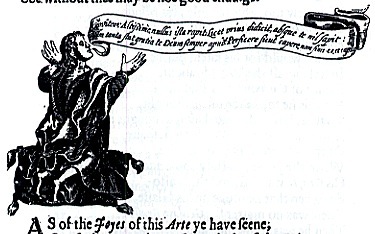
不幸の最初の原因は、多くの者がこの術を探求しながらも真理に到達しうる者はほとんどおらず、また、学び始める以前より教え導かれなければ真理に到達しえないことを、心底痛感するところにある。他者の導きによって真理を悟る者、それについてはっきりと思い知らされるのである。いとも深甚なる万物の秘奥についての伝授を望む者は、自然界に存する相違という難解な影をよく学ばねばならない。それについて述べるに、どんな言葉を綴ろうとも、誤謬から学徒を守りうるほどに正確なものにはなりえないのである。今はもう生を終えた多くの者たちは、ついに我らが石の探索を成し遂げるまでに、あまねく道に迷ってきた。かなり初期の段階から、作業の最終段階まで、すべては誤りやすく、経験者からの導きによって啓発されねばならず、適した正しい熱気と冷気についても教練されなければならない。大胆で、自信過剰な探求者ほどこのことが解っていない。我らの術は、完遂に焦りすぎる者からその作業を徒爾に終えるが、成功に至る者は慎重に注意深く取りかかる。最も嘆かわしい状況は、いったん間違いを犯せば、如何なる作業過程の段階にあろうとも、ことのはじめから全てをすっかり、やり直さねばならないことである。それゆえ、この探求を断念する者は誰しも、心痛に遭遇することを予期せねばならないのである。学徒は、新しい発見にあわせて針路を変更せねばならないこともある。その実験は失敗に転ずることもあり、心中は疑念と混乱の状態に陥ることもある。かくして学徒は、最終的に望む終局に至るまで、矛盾する結果に苛つかされ続けることであろう。錬金術師の悲嘆と不幸について更にもう少し語ろう、この術の実際を獲得しようという汝の欲求を、少なからず和らげることにもなろう。まず、よく賢者らの言にあるように、我らの術の完全な案内者を数多の詐欺師たちの中から探し出すのはたいへん困難なことである。そして、真実これに精通している達人を見つけ出したとしても、汝がこれから経験するであろう避けえぬ憂悶がすっかり払拭されたわけではないのである。
もし汝の心が美徳に忠実であれば、悪魔は全力を尽くして汝の探求を阻止するであろう。性急さ、絶望、欺瞞という、相次いで仕掛けられる三つの躓きの石がこれであり、悪魔が恐れるのは、汝がこの秘奥に通じて良き作業に成功することなのである。第一に、あまりに性急にことをなそうとするところに罠は潜んでおり、これが汝の作業をひどく損なうことになる。『哲学者の饗宴』という小品にもあるように、この術について記したあらゆる著者たちは、度の過ぎた癇性は悪魔のなせるところであると口を揃えて言っている。そのようにして悪魔は、作業の早い段階に於いてすら、少々の遅滞を気に病む者に素早く終止符を打つのである。しかし賢明に振る舞う者は、急がば回れの格言が示すほんとうの価値に気付くことであろう。性急さに取り憑かれた者の作業は、一ヶ月経てど一年経てど完了できない。急く者に不満の種の無きはなし、それがこの術に於けるひとつの真理なのである。冷静な者たちは、性急さが真実の頂点から汝を身投げさせる悪魔の狡猾な罠であり唆しであることを確信している。性急さは、正しい路から我々を逸らす鬼火である。冷静沈着な者は、おのれの癇性へと気丈に面を向けている。そうした者たちの振る舞いは節度のあらわれであるけれども、それは性急さというものが術の作業のすべてを妨げるものだからである。努々、性急さは悪魔の罠と知り、身を守るがよい。作業に急く気質を助長する過度の熱情については、以上が充分な注意となろう。多くの者たちが、自らを鋭い悲しみで貫き刺している。それは、彼らが性急にすぎるからであり、究極へ至らんとして取り乱しているからなのである。こうしたことは妖魔の誘いから生じていることなのだ。性急さというものについてはこれ以上語るべきところは無いが、忍耐力こそが天恵の者には相応しいとだけここに加えておこう。そして、我らの敵は性急さで汝を拉ぐことが出来なければ、今度は虚脱によって汝を襲うであろう。これは汝の心を継続して落胆の思いに陥れる。そもそも、成功する者がほんの幾人かしかいないにもかかわらずこの術を求める者のなんと多いことか。そしてその中で、おのれよりもずっと賢い者たちにすらが手抜かりがあったのであろう、などと思う。それで、大いなる秘奥を己が手に入れることになぞ、何の希望が残されているというのか、という疑念に至る。更に、汝の師匠が必ず与えると約束した秘奥を、実際彼がもっているものなのか、あるいは師は、知っていることの最も良い部分を汝から隠し立てしないものかどうか等々。かように疑いの念は汝を苛むであろう。邪悪なるものは、不信と落胆で汝を目的から逸らそうとこれらの疑いで汝の心を満たそうと努める。その攻撃に抗しうるものは徳性から鼓吹される静かなる信頼、堅実で思慮深い推論だけである。汝の師匠や導師の高潔さを沈思すれば、汝の恐れは風に散るであろう。師は、愛と献身によって汝を導くために現れたのである。そのことに思い至るならば絶望する必要など何もあるまい。確かに、奉仕を申し出てくる者を信用するのは難しいものである。そういう人物はこちらが求めるよりも多くをこちらに求めてくることが常であるからだ。けれども汝の師が、私が汝に求めるよう示した如くの人物であり、その師もまた汝を待ち望んでいたのであれば、汝は不信の矢に堅固な防備を築かねばならぬ。そして汝の師が、まったくもって私の師匠のような人物であれば、汝の師に対する疑いは許されざることとなろう。我が師は高潔な人物であり、真実を愛し、義に篤く、欺瞞の敵であった。さらに秘奥の良き保護者であり、仰々しく知識をひけらかす者あれば知らぬ振りで平静を装い、師の元で薔薇の色について語る者があれば、彼は容易に踏み込めぬ重い沈黙をもって傾聴していたものであった。私が長年付き従ったのはこういう人物であった。だがこの師も、私が多くの試練を乗り越えて素質を証明するまでは、何一つ重要なことを与えてはくれなかったものである。私が心から真実に忠実な者であるとわかり、大望を心に秘めていることを見て取るや、師はその眼に神の意志より来る恩顧を宿し、私に心傾けたのであった。こうして師はついに、私への秘儀の伝授が一刻も遅れるべきではないと思い至った。私の学んだことが充分であり、汚れのない魂が師の心を動かしたのであった。師は筆をとって以下のように書簡をしたためた。「信義篤き我が友、親愛なる同胞よ。我は汝の要求に応ずることに逆らえぬ。もはや汝の如き人物は我が前に現れることはなかろう、汝、我が恩顧を受ける刻は来た。汝の雄渾なる気骨そして篤き信仰、世人の認める徳と叡智、汝の誠実と愛と忍耐、志操堅固、汝の魂の高潔なる大望。汝の素晴らしき精神のありさまに今こそ我は報いよう。永遠に続く汝の慰安と安楽に、力強き秘奥を開示することによって。この目的のために、口頭にて汝と会談するの要あり。もし我が汝に記述にて示せば、それは我が誓約に反することとなる。ゆえに我らには会うことが必要である。汝が来たるときには、我は汝を我が術の継承者とし、我はこの地より去ろう。汝はこの偉大なる秘奥に関しての我が同胞、我が跡取りとなる。このゆえに、この書信を受けたことを神に感謝したまえ。継承権を得るよりも、戴冠されるほうがよい。神が御自身の天界の聖人に次いで列する者のみが、そのあまりに高き道義によって、必ずやこの術を継承する。今はもう我は汝にこれ以上書かない。今すぐに馬に跨り、我がもとに来たれよ。」私はこの書簡を読み終えるとすぐに出立し、距離は百マイル以上であるにもかかわらず、我が師匠の元へと馳せ参じた。私は師に従って四〇日を過ごし(私はこの王国における他のあらゆる人物に引けを取らぬほどに、斯道を心得てはいたけれども)錬金術のあらゆる秘奥を学んだ。しかし、作業そのものが四〇日のうちに完了すると考えるのは愚かなことである。私はその時間で充分に指導されたが、作業そのものは長い期間を要したのである。。開かれた自然の門の秘密とは、闇に沈んだあらゆるものが光の如く澄み渡ってゆくものであった。私は万物の原因と理論とをまざまざと目前に見た。私にとっては、それは疑うことも諦めることも、もはやかなわない。もし汝が私のように運良く導師を得れば、汝は決して落胆に襲われることはあるまい。
汝が身を守らねばならぬ第三の敵は欺瞞である。これは前述したふたつよりも恐らくはずっと危険なものである。汝が炉を燃焼させるために雇わねばならぬ傭僕は、最も信用ならない人物である場合がある。不注意な者もいれば、炎に傾注せねばならぬ折に居眠りを始める者もいる。能う限りの害悪を汝にもたらす無法者もいる。さらに愚か者であったり、自惚れの強い自信過剰は言いつけに従わない。他人の所有物に手を伸ばす者もあれば、酒飲みであったり、怠慢な者、注意散漫な者もいる。大きな損失を免れようとするのであれば、こうした者たちすべてに注意しいなければならない。忠実な傭僕はおしなべて無知なものである。機転の利く者はたいがい誤りを犯す。そして小賢しい者と愚かな者のどちらが邪であるのかは、俄には判別し難い。実験のすべてがつつがなく行われていた折、傭僕が材料と器具を盗んで逃げてしまい、ただ空の工房に残されたという経験が私にもある。そして出費や時間、さらにもう一度はじめから作業を行う算段をしたとき、私は打ちのめされ、錬金術というものには二度と関わるまいと、ほとんど決心しかけた。たとえ十人の信用しうる人物が事実の証明のために残っていたとしても、私が如何にすっかり手にしたすべてを剥ぎ取られたかは容易には信じられまい。じつにその一撃は強烈であり、ひとの身が悪魔に唆されてこれに共同することなしに可能なものではとてもありえない。私はまた生命のエリクサを造り、これもさる商人の妻に奪われ、多くの貴重な調合物から第五元素を得たが、こうした邪な連中にあらゆるものを奪われ、私は、この世の享楽の甘美な器には、寛大な痛恨が注ぎ込まれるということを知るようになった。この作業の難局について、まだ言い尽くしていないことをいま少し語ることとしよう。私が考えている惨禍は信心深き善人に起こるものであり、そして私こそがそれを説明しうる唯一の人物である。
信仰深き神の僕トマス・ダルトンは、英国人の中でも比類なくかなりの量の赤き医薬を持っていた。あるときトマス・ハーバートというエドワード王室下のさる騎士が、このダルトンをグロスターシアの修道院から実力行使で連行し王の御前に引き出し、そこで彼はデルヴィスに引き合わされた。秘書ウィリアム・デルヴィスはダルトンが書簡を送った人物であるが、これがダルトンの術の才覚を王に話してしまったのであった。デルヴィスは、いつもエドワード王の御前に仕えている忠実な僕であり、彼はダルトンがたった一時間で王国の貨幣と完全に一致する一千英貨ポンドの金を造ったと断言し、聖書の最も聖なる宣誓によってこの証言を強調した。このときダルトンはデルヴィスを見据え、「嗚呼、デルヴィス、汝はすでに誓いを破った! 汝は余に誓った起請を卑劣にも打ち破り、主を裏切ったユダのごとく余を裏切った!」と言った。デルヴィスはこれに応え、「はい、その通りです。貴方の秘密を裏切らぬことを、いちどは貴方に誓いました。しかし私は自分が偽誓の罪にあるとは思いません。王と国家への奉仕が、私を誓約から解放してくれるからです。」するとダルトンは沈着にこれに答えた。「その口実では、汝の大罪は許されぬ。それだけで逃れられるならば、面前にて偽証した汝を王御自身が信じ得ようか。更に、」彼は王に向かって続けた「永きに渡って私がこの医薬を手にしていたことは認めましょう。しかしついにそれは私にとって悲嘆と苦悶の源にしかならなかったのです。それであの修道院に隠棲した後、私はそれを、日々に海の満ち干が洗う入江へと投げ込んだのです。かくして、聖墳墓を奪還する二万の騎士を完全装備させるに充分な財貨は失われました。神への帰依のもとに私はこの医薬を長年保持してきましたが、それはこの遠征にとりかかる王を援助するという一貫した目的があったからでした。しかし、今ではこの聖務は忘れられ、医薬もまた失われたのです。」王はかように驚くべき宝物を放棄したことを愚かであったと云い、新たに医薬を調合するようダルトンに命じた。「いいえ」とダルトンは応え、「それは決してできないのです」と言った。「なぜだ」王は問う、「如何にして汝はそれを手に入れたのだ」と。ダルトンは、リッチフィールドの該博なカノン(司教座聖堂参事会員)から受け取ったと応えた。彼は長年勤勉にその作業に従事し、ついにその師が、持っていた医薬のすべてを彼に授けたということであった。これを聞いて王はダルトンに四マークを与え、望む何処にも去ってよいとして自由を与えた。別れに際して王は、これまでダルトンとの縁を得られなかったことに遺憾を述べるのであった。ところが、王の従者たちの中にはしばしば卑劣な暴君がいるもので、騎士ハーバートはダルトンを捕らえて王の与えた財貨を奪い、ステップニーに拉致して長く留置したのである。その後、密かにグロスターシアの城に運ばれ地下牢に投獄され、四年の間を囚人とともに過ごし、その間ダルトンはハーバートの思い至るところあらゆる方法で拷問された。とうとう処刑されようというときダルトンは、牧師に向かってこういった。「嗚呼、神聖なる主キリストよ、私は長く貴方から引き離されていました。貴方は私にこの知識を与え、そして私は傲慢な自尊心なしに使いました。私はこの叡智を遺すに適する人物を見出すことが出来ませんでした。それゆえ、最愛なる主よ、私は貴方の賜物を、貴方の手に返します。」彼は敬虔な祈りを述べると処刑人に微笑んでこういった。「さて、汝のすべきことをしなさい。」このときハーバートは、目に涙を溜めながらこれらの言葉を聞いていた。欺きも投獄も死もこの犠牲者を屈服させることなく、尊き秘密を引き出すことがなかったからである。そして彼は下僕らに命じて、その剛毅が屈服されることのないままに老人の縛めを解かせた。ダルトンは起き上がって悲しい眼でハーバートを見ると顔貌に失望を浮かべ、重い心とともに死んでいった。彼はこれ以上生きながらえる年月を望まなかったからである。この危害は不敬なる輩の欲と、残虐さを通じて彼に及んだのであった。この後ハーバートは長からずして死に、デルヴィスはテュークスベリーでその人生を終えた。こうしたことは、この術の知識を熱望する者たちの受難であり、それは堪え忍ばねばならぬ命運として我らの前に横たわっている。しかし、我々は邪悪な輩の欲望がいかに彼ら自身に仇なすかもまた知っている。もしハーバートが、残虐と不遜、暴力のかわりに、ダルトンを親切に丁寧に扱っていたら、それは王のみならず国家全体から、より多くの利益が報いられたことであったろう。この王国の隅々は罪業に支配されている。だから我々は、友愛が常のことでないからといって、それを不思議に思う必要はないのである。さもなくば、騎士、司祭や市民たちの施しは、人々を物価や租税から解放して救済するはずなのである。ゆえに我々は品行の悪い暴力に叡智の獲得は許されぬことを学ぶ。徳と悪はそれぞれに反対であり、片方に身を委ねる者は他方から報われることはない。もし邪悪な人物がこの術の知識を全て手に入れれば、その際限なき暴慢は耐えられぬほど大きくなり、そしてその野心はあらゆる範囲を超えるであろう。これを手段に彼らは以前より悪い人物となる。さて、我らの術の喜悦と苦痛について述べてきたこの章は終わりである。次なる章では我らの石の構成要素を明らかにしよう。

